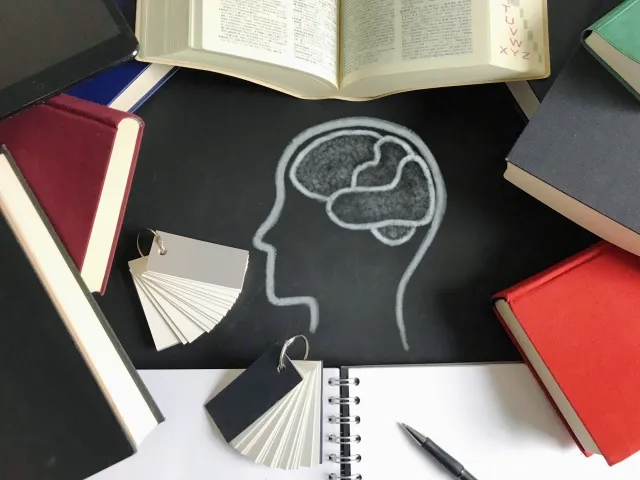「さっき覚えたはずなのに、もう忘れちゃった…」そんな経験は、誰にでもあるのではないでしょうか?
実は、私たちが「物を覚えること」や「忘れてしまうこと」には、ちゃんと理由があります。それは、脳が記憶を扱う仕組みによって決まっているのです。
たとえば、テスト前にがんばって暗記しても、時間がたつと少しずつ忘れてしまうのは、脳の“お掃除システム”が働いているからかもしれません。でも、この仕組みをうまく使えば、「忘れにくい記憶の作り方」もちゃんとできるのです。
この記事では、そんな記憶のふしぎや、なぜ私たちは忘れるのか、そしてどうすれば記憶をもっと上手に使えるのかを、わかりやすくご紹介していきます。
1.記憶ってどうやって作られる?

私たちが何かを「覚える」とき、実は脳の中ではいくつかのステップが行われています。記憶は、次の3つの段階に分けて考えることができます。
① 感覚記憶(かんかくきおく)
まず、目や耳などから入ってきた情報は、「感覚記憶」という短い記憶になります。たとえば、誰かが話している声を聞いたとき、話の内容を一瞬だけ記憶しているのがこれです。この段階の記憶は、とても短く、数秒で消えてしまいます。
② 短期記憶(たんききおく)
感覚記憶の中で、「これは大事そう」と思われた情報は、「短期記憶」として脳に少しだけとどまります。短期記憶は、たとえば電話番号を一時的に覚えておくような記憶です。ただし、この記憶も10~20秒ほどで消えてしまうことが多く、ずっと覚えているには工夫が必要です。
③ 長期記憶(ちょうききおく)
短期記憶をくり返し思い出したり、意味を考えたりすると、「長期記憶」としてしっかり定着していきます。長期記憶は、何日も、何年も覚えていられる記憶です。好きな歌の歌詞や、自分の誕生日など、忘れにくい記憶はここにあたります。
このように、記憶は「一瞬 → 数秒 → 長く覚える」という流れで作られているのです。

だからこそ、勉強したことを長く覚えておくためには、「何度もくり返すこと」や「自分の言葉でまとめること」がとても大切なのです。
2.なぜ人は忘れるの?
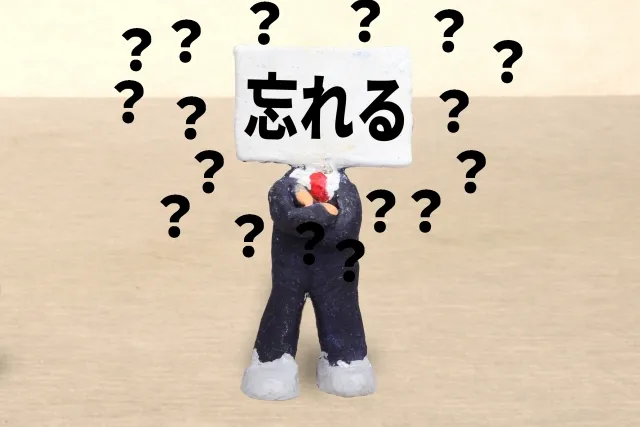
せっかく覚えたのに、気がついたら忘れてしまっていた…。そんなとき、「どうして忘れちゃうの?」と不思議に思ったことはありませんか?

実は、私たちの脳には、「すべての情報をいつまでも記憶しておくこと」はできないしくみになっています。忘れるということも、脳にとってはとても大切な働きなのです。
エビングハウスの忘却曲線
ドイツの心理学者・エビングハウスが発表した「忘却曲線」という研究によると、私たちは覚えたことを、時間がたつほどどんどん忘れてしまうことがわかっています。
たとえば、意味のない言葉を覚えたとき――
- 20分後には約42%を忘れ、
- 1時間後には約56%、
- 1日後には約74%を忘れてしまう
という結果が出ているのです。
これを見ると、「人の脳って、けっこう忘れやすいんだな」と思うかもしれません。でも、これは私たちが必要のない情報を整理するための、自然な働きでもあります。
干渉による忘却(じゃまが入ると忘れやすい)
また、記憶が消えてしまう原因には、「情報のじゃま」が入ることもあります。これを「干渉(かんしょう)」と呼びます。
たとえば、朝に覚えた英単語を、昼にたくさんの別の言葉を聞いたり見たりすると、記憶が混ざってしまって忘れてしまう――そんなこともあるのです。
- 順行干渉:前の情報が後の記憶をじゃまする
- 逆行干渉:後の情報が前の記憶をじゃまする
忘れるのは“悪いこと”じゃない?

ところで、「忘れる=悪いこと」と思いがちですが、実はそうではありません。
私たちの脳は、必要な情報と、そうでない情報を見分けて、いらないものを“整理”する役割も持っています。
この“お掃除機能”が働くおかげで、大事なことに集中できるようになるのです。
ですから、「忘れること」も、脳がしっかり働いている証拠とも言えるのです。
3.記憶を長く残すコツ

「せっかく覚えたのに、すぐ忘れてしまう…」そんなお悩みをもっている方は多いと思います。でも、ちょっとした工夫をするだけで、記憶はぐんと長持ちするようになります。
ここでは、勉強や日常生活にもすぐに使える、記憶力アップのコツをご紹介します。
① 間隔をあけてくり返す(間隔反復)
人の記憶は、「何度もくり返すことで強くなる」という性質があります。でも、ただ同じ日に何度も読むより、時間をあけて思い出す方が、記憶には効果的です。
これを「間隔反復(かんかくはんぷく)」といいます。
たとえば、
- 1回目:今日勉強した内容を覚える
- 2回目:1日後にもう一度確認
- 3回目:3日後にテストしてみる
というように、少しずつ間隔をあけて復習すると、記憶がよりしっかり定着しやすくなります。
② イメージやストーリーにする
覚えたいことを、ただ文字だけで読むのではなく、「イメージ」や「ストーリー」にしてみると、記憶に残りやすくなります。
たとえば、英単語「apple(りんご)」を覚えるときに、「真っ赤なりんごを手に持っている自分」を思い浮かべるだけでも、記憶に残る力がアップします。
また、歴史の年号などを「漫画のストーリー」や「お話」にして覚えるのも、とても効果的です。
③ 寝る前に復習する
実は、「寝ている間」にも、私たちの脳は記憶を整理しています。とくに、寝る直前に見た情報は、記憶に残りやすいことが知られています。
だからこそ、テスト前などには「寝る前に軽く復習する」のがおすすめです。ただし、夜更かしは逆効果なので、無理せず少しだけにしましょうね。

このような方法を取り入れることで、「忘れにくい記憶の作り方」がだんだん身についてきます。自分に合ったやり方を見つけて、ぜひ試してみてくださいね。
4.年をとると、どうして忘れっぽくなるの?

「うちのおばあちゃん、最近よく物を忘れるのよね」そんな話を聞いたことはありませんか?年齢を重ねると「物忘れが増えたなあ」と感じる方が多くなります。でも、これは誰にでも起こる自然なことなのです。
脳も“年をとる”から
私たちの体と同じように、脳も年齢とともに少しずつ変化していきます。記憶に関係する「海馬(かいば)」という部分や、「前頭葉(ぜんとうよう)」という脳の働きが、ゆっくりと弱まっていくことがわかっています。
すると、こんなことが起こりやすくなります。
- 名前や予定を思い出すのに時間がかかる
- さっき聞いたことをすぐに忘れてしまう
- 会話の途中で「あれ?何を言おうとしてたんだっけ?」となる
でもこれは、病気ではなく、自然な“加齢による変化”です。たとえば、筋肉が少しずつ弱くなるように、脳も少しずつスピードがゆっくりになっていくのです。
使えば使うほど、元気を保てる!
うれしいことに、脳は年をとっても「使えば使うほど元気を保てる」という性質があります。本を読んだり、会話をしたり、新しいことにチャレンジしたりすることで、記憶力を支える力が長く保たれることが、最近の研究でも分かってきました。

「脳のトレーニング」は何歳からでも遅くありません。ご家族で一緒にクイズをしたり、思い出話をしたりするのも、とても良い刺激になりますよ。
5. 最新の研究と、未来の記憶の話

記憶についての研究は、いまも世界中で進められています。「どうすればもっと効率よく覚えられるか」や、「記憶がうまくいかない病気をどう防ぐか」など、科学者たちはさまざまなテーマに取り組んでいます。
ここでは、最近注目されている研究や、ちょっとワクワクするような未来の話をご紹介します。
記憶は「電気信号」と「つながり」でできている
私たちの記憶は、脳の中にある神経細胞(ニューロン)たちの「つながり(シナプス)」によって作られます。このつながりが強くなることで、「覚えた!」という状態になります。
最近の研究では、このシナプスの変化をリアルタイムで観察する技術が進んでいて、脳の中で記憶ができる“瞬間”を科学的に見ることも可能になってきました。
脳にチップを入れて記憶力アップ…?
アメリカでは、「脳に小さな装置を入れて、記憶力を助ける」という研究も行われています。これは、病気などで記憶がうまく働かない人をサポートするためのもので、脳の活動をモニターしながら記憶のしくみを補うことを目指しています。
もちろん、まだ一般には使われていませんし、安全性のチェックもこれからですが、「記憶を助ける機械」というのはまるでSFの世界のようですね。
記憶を“書き換える”未来も…?
さらにびっくりするのは、「記憶を書き換える」ことができるかもしれない、という研究です。
たとえば、いやな体験を思い出すとつらくなることがありますよね。そんなとき、脳の中の「いやな記憶だけ」を少しずつ和らげたり、感じ方を変える技術が開発されつつあります。
これは、心の病気(PTSDなど)に悩む人を助けるための研究ですが、未来にはもっと広く応用される可能性もあるのです。
こうした研究が進むことで、記憶のしくみがさらに解明され、私たちの生活にも役立つ日がくるかもしれません。

記憶は、まだまだたくさんの“ナゾ”に包まれた、ふしぎで奥深いテーマなのです。